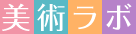物質感の強い油絵は完成後に存在感を放ち、ただの教材ではなく、手元に置いていつまでも楽しめるインテリアにもなります。
この講座では、「自由に描く」よりも一歩踏み込んだ、論理的なプロセスに基づいた絵画メソッドを学んでいきます。描く手順には理由があります。理論に裏打ちされた方法で、油彩画をしっかりと身につけていきましょう。
伝統的な色彩理論や描画手法を踏まえつつ、それらを現代的に実践しやすい形へと磨き直しました。確かな土台のうえに、独自の工夫を加えた内容です。
本講座は、油彩による絵画空間の構築を習得することを目的としています。鉛筆デッサンなどの基礎練習を中心に行うものではありませんが、初めての方も安心して取り組めるよう、下絵やプロセスをご用意しました。油彩の奥深い魅力を、すぐに体験していただけます。
絵具の本質と支持体の色

「絵具」は単なる色ではなく、物質としての性質を持っています。混色の理論上ではできるはずの色が、実際にはうまく発色しないこともままあります。この“ズレ”を理解することは重要です。

本講座では、着彩された支持体(描かれるもの)を使用します。キャンバスや紙などの支持体は、日本では白いものが多く使われ、また販売されています。しかし、対象の立体感や、よりリアルな表現には、中間色を利かせた有色地が有利に働きます。こうした点を有効に活かして描写のトレーニングに取り入れています。

絵画技法は、文化の違い(日本では紙や絹地に墨を用いることが多い等)や、地域ごとに手に入りやすい材料にも影響されてきました。油彩画の本場である欧州では、古くから褐色や青灰色等に着色をした下地が、素描や絵画を問わず多く使われてきました。このような歴史的背景も学びながら、合理的なテクニックを理解します。
具体的な練習の流れ

必要に応じて、ご自身で三色を組み合わせるカラーチャートの作成もします。これは絵具の色味の関係を理解するための、とても効果的な方法です。

いくつかの代表的なモチーフ(例:果物、布、静物など)を取り上げ、それぞれに適した、チャート化された描き方を身につけます。描きながら“パターン”を整理していくことで、自然と「描き方」の引き出しが増えていきます。

はじめは、こちらで用意した下絵(線画)を使い、それを支持体にトレースするところから始めます。構図に悩まず、モチーフの表現に集中できるようにしています。
油彩だからこその魅力

使用する絵具は油彩です。アクリル絵具のようにすぐ乾く心配がなく、ゆっくり描き進めることができます。とはいえ、乾きの遅い油彩では、急いだ作業では画面上の絵具同士が混ざってしまい、はっきりした上描きや、細かい描き込みがしにくいイメージもあります。

本講座では、紙やMDFボードの支持体を使用することで、余分な油を支持体に吸わせ、画面の乾きが早まったような状態をつくり出します。これにより、上描きもスムーズになり、制作の自由度が高まります。

もちろん、絵具の量の加減で、油彩ならではの混色やグラデーションも可能です。たっぷり絵具を使い、画面の中で色をつくっていく感覚を楽しんでください。
完成後